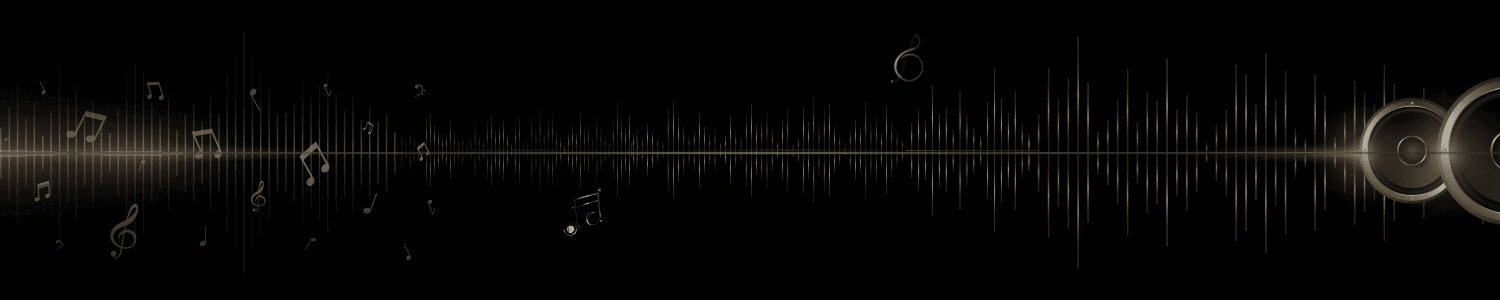“高音質”にも好みがあるという前提から始めよう
ハイレゾ音源と聞くと、「とにかく音がいい」「CDよりすごい」というイメージが先行しがちです。たしかにハイレゾは、CDよりも高いサンプリング周波数やビット深度で収録された音源であり、情報量が多く、空気感や臨場感をより繊細に表現できます。
しかし、「どのハイレゾ音源でも感動できるか?」というと、実はそうでもありません。音楽のジャンル、録音の質、マスタリングの方法によって、ハイレゾの“向き・不向き”があります。さらに、聴き手の好みやリスニング環境によっても、感じ方は大きく変わってきます。
ハイレゾを最大限楽しむためには、まず“自分にとっての心地よさ”を明確にしておくことが大切です。自分はどんな音が好きなのか。何に感動するのか。そこを起点に選ぶことで、ハイレゾ体験はぐっと豊かになります。
ジャンルごとに違う“ハイレゾ映え”するポイント
ハイレゾの恩恵を感じやすいジャンルと、そうでないジャンルがあります。たとえばクラシックやジャズ、アコースティック系の音楽は、録音環境や演奏者のニュアンスが音に直結するため、ハイレゾとの相性が非常に良好です。ホールの響き、弦のうなり、ブレスの息づかいまで細やかに感じられます。
一方で、EDMやロックなどのジャンルでは、もともと音作りの段階でエフェクトやコンプレッサーが多用されており、音のダイナミクスがやや圧縮されがちです。こうした場合は、ハイレゾの高域の伸びやステレオ定位の広さが「違い」として現れますが、人によっては“あまり変化を感じない”という印象を受けるかもしれません。
また、ボーカル重視の楽曲を好む人には、ハイレゾの「定位の明確さ」が特に魅力的に映るはずです。中央にピタッと定まった声、伴奏との距離感、リバーブの奥行き。こうした要素が明快に分離して聴こえるのは、ハイレゾならではの体験です。
“音源選び”は“音楽選び”の楽しみに変わる
ハイレゾ音源は、同じアーティストの楽曲であっても、配信サイトによってマスタリングが違っていたり、24bit/96kHzと24bit/192kHzで収録されていたりする場合があります。どちらが良いというよりは、“自分にとっての聴きやすさ”を基準に選ぶことが大切です。
たとえば、オフィスや作業中に聴くなら高域の情報量が多すぎると疲れやすく、少しソフトめのチューニングのほうが心地よく感じられるかもしれません。逆に、自宅でしっかりと腰を据えて聴く場合は、空間描写や音像のリアリティがある音源のほうが“浸れる”体験を得られるでしょう。
最近では「ハイレゾおすすめ特集」や「リマスターハイレゾ」などのキュレーションも充実しており、そこから自分の好みに合いそうなアーティストやアルバムを見つけるのも楽しいプロセスのひとつです。
大切なのは、“ハイレゾ音源”というフォーマットそのものに価値を求めすぎないこと。良い音には必ず“自分の好きな音”という軸があり、それを知ることこそが、最高のリスニング体験への第一歩になります。